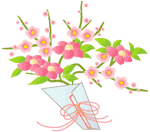小説・花暦

■■過去からの電話■■
しばらくして電話がかかってきた。敦子が帽子を忘れていっていたのでそのことだろうと調子の良い声で電話に出た。
「もしもし、奥様でしょうか?」
先方の声に聞き覚えはない。
「そうですけど」
「私は4年前に一度お手紙を差し上げたものですけど、今日は奥様にお会いしたくて電話をしました。」
奈緒美は4年前に一度電話をかけてきた女性がいたことを忘れてはいない。
夫、祐司のことを手紙に書いて送ったから読んでほしいといってきた女性がいたのだ。
手紙に差し出し人の名前を書かなかったからと
ご丁寧に届いたとき奈緒美が驚かないようにと電話をかけてきたらしい。
「どういうことでしょうか?」
とたずねると、
「手紙を読んでください」
と応えるだけで他を語ろうとしない。失礼な話である。
「こうして電話くださったということは、主人とはどういう関係でしょう。」
「手紙を読んでもらえば分かります」
女性職員が多く接待の多い仕事なので、これまでも主人に対する愚痴や飲み屋からのわけの分からない電話
信販会社からの督促電話など自宅に入ってはきているが、すべて祐司に伝えて、
会社関係の事にはかかわらないようにしてきている。
これまでも、祐司が奈緒美に仕事の話をしないでいるのだから、
おかしなことがあっても聞くこともできないし、おかしなことがあったときも「知らない」の一言で終わった。
それがきっかけで奈緒美は祐司を自分の心から開放しようときめ、
夫であるより会社の上司である主人を盛り立てていこうと考え、家庭内のごたごたも言わなくなった。
そうする事が自分自身も束縛されずにすむのだと自分に言い聞かせながら。
祐司は家庭に帰ればよき父親であり、よき夫なのだ。
大病を患ったこともありそのときから月に一度は家族とのコミュニケーションを持つようにもなった。
その中で自分の趣味も持ち、大黒柱としては申し分のない地位を維持し、成長していく子供たちから見ても、
父親の努力は尊敬に値するところとなっている。
頼りになる父親がいて、いつもにこやかに笑っている母親がいる家庭は、
病弱でまともに働けない父親とその代わりに朝から仕事に行き、
夕方から暗くなるまで田畑にはいつくばって働き、帰ってきたら
「こんな時間まで何をしてた」
と腹を立てて怒り出す夫の横暴に、
まるで召使いのように尽くす母親の姿を見て育った奈緒美の小さい頃からの理想だった。
その母親が祐司を実の兄姉やその配偶者の誰よりも高く評価してくれているのだ。
「貴方と主人の関係は仕事関係ですか?金銭関係ですか?」
何も言わない電話の向こうの相手に問いかけた。
「いいえ」
奈緒美は一呼吸して
「男女関係でしょうか?」
というとあっさり
「そうです。奥様にその手紙を読んでほしいのです」
といいきった。
奈緒美は回りくどい話は嫌いなのでここで決着をつけようとおもっていた。
「貴方は私の家庭内の事情を聞いていらっしゃるでしょうか?
主人は仕事上のことは家庭に持ち込まないので私は何も分からないし、主人が聞いてこない限り
手紙をいただいた事主人にも言いませんよ」
「とにかく読んでください」
その女性はそういって受話器を置いたのだ。
気分の悪い話だった。
奈緒美はその手紙を数時間後に郵便受けから取り出すと
しばらく瞑想した後、祐司に連絡を入れた。
直接話しをするには、どこか場所を探さなければならない。
子供たちの前で話せる内容ではないし、奈緒美自身関りたくも無い事だった。
祐司は代わりのない声で
「どうしたの。」
とかえしてきた。
「今日ね、名前を言わない女性から私に手紙を読んでほしいって電話があって
その手紙が届いたんだけどどうしたらいい?」
出来るだけ冷静な声でそういうと
「読まなくて良いんじゃない」
祐司もまた取り乱した様子もなく平静を保っているようだ。
「そう、じゃ後で渡しますから貴方が処理してくださいね。」
その手紙を受け取った祐司はというと、何の弁明もなく、当たり前のように仕事に行き
子供たちとふざけあったりと自分のスタイルを変えなかったので
いつの間にか解決したものと思い、
その年には転勤が決まり単身で家を出て行ったので
多少の傷跡をもちながらもなんでもないように暮らしてきた奈緒美だった。
あの日から4年の年月が過ぎた今日、その女性はまた奈緒美に電話をかけてきたのだ。
「私は貴方にお会いする気はありません。ご存知でしょうけどあの手紙も読んでおりません。」
奈緒美はやっとの思いで平静を保っている。
4年前の傷口がやっとふさがり、以前の生活に戻りつつある今、また同じ人物からの電話を受けているのだ。
「奥様に会えば私自身の気持ちに踏ん切りがつけられると思うのです。
今、病院に通って薬を服用しています。」
「病院ですって 何の病院ですか?」
応えれば相手の口に乗ってしまうと思いながら聞き返すと
「精神科です。どうすればいいのかわからないんです。」
しばらく沈黙した後
「それならなおのこと、私ではなく主人と話し合ってください。私は、以前にも申しましたように
電話をいただいた事も主人には話しませんよ」
そういいながら、ことが深刻ならば妻として無関心を通す事で夫を守らなければならないとも思ったし
電話の主が精神的にまいってて、奈緒美と会うことで踏ん切りをつけようとしているならと心が揺れていた。
「あの人には今日、奥様に会うといいました」
電話の主は何を考えているんだろう。奈緒美にはその女性の心がつかめない。
「主人は何といいましたか?」
「勝手にすれば」
といわれました。
奈緒美はあきれていた。一瞬、二人がぐるになっているのではと思った。
そうなるとだんだん名前も知らぬ相手が何者かを知りたいと言う気になっていた。
不思議と気持ちも落ち着いてきている。
何も知らされていない妻のところに行くという女に勝手にすればといった祐司の心もつかめない。
もう一人だ。誰をかばう必要もないし、瞬間的に今は子供たちと自分の生活を守ることが一番大切なことだ
と腹をくくっていた。
「私はこれから用事がありますので今すぐにはお会いできません。
あなたも冷静になって、もう一度会う必要があるか考えてくださいませんか。」
そういって受話器を置いた。

放心状態のまま、外出の準備をしようとしているところにインターホンがなり
「奈緒美ちゃん、?アッ子だけど帽子忘れてなかったかな?」
鍵をかけ忘れていた玄関を開けながら塩見敦子が声をかけた。
「どうしたの奈緒美ちゃん。顔が真っ青だよ」
居間のソファーにおいてあった敦子の帽子を持って奈緒美が現れると
心配そうにたずねた。
「なんでもないわよ。」
無理に笑おうとしているのがわかったのか、そのままあがりこんできた。
「なんでもない顔じゃないわよ。さっきとぜんぜん違うもの。」
「サア、話しなさいよ。気持ちが楽になるから・・・・そんな顔して外には出れないでしょう
ホラ、危ない!足元もふらついてるじゃない。さあ、すわって」
だてに二世帯家族の中心に立っているわけではない敦子の勢いに押されるように
へたへたと座り込んでしまった奈緒美だったが、暗闇に光を得たような思いがして
今、このときに敦子が来てくれた事に何か意味があるように感じていた。