季節(とき)のワルツ

■■季節の始まり■■
その夜の夕食後、美園はお風呂から上がってきた祖母の愛子に昼間あった韓国の青年のことを話してみた。
「その人ね、キム・ソルジュって名前なんだけど、朝方その前の川原でずっと座り込んでいた人だったんだ。
それでね、私ずっと考えてたんだけど、
小さいころママにそこに住んでたおじさんの話し聞いたような気がするの。」
愛子は美園が出してくれたオレンジジュースで口を湿らすと昔を懐かしむように静かに語り始めた。
「確かにこの川原に30年ほど前まで小さな小屋が建っていたのよ。その人は日本名を金木さんっていってね。
おじいちゃんの戦前からのお友達よ。私は戦後、後妻に入ったからあまりそのころの
詳しいことは知らないけど、炭鉱で働いているときに知り合ったみたい」
「ふ〜ん、おじいちゃん炭鉱で働いてたんだ。」
美園は愛子の昔話に物書きとしての興味がふつふつと沸いてきて
「じゃあ、その人韓国から無理やり連れてこられた人だったの?」
「そうだね、その時代はそういう悲しいことがたくさんあったんだよ。
その人のことキンさんて呼んでたんだけどね、お国には家族がいて、奥様やお子さんのことを気に病んでた。」
「戦争が終わって法律がかわったものだからお国に帰りたくても帰れなくなってしまって、
おじいちゃんの住所を頼りにこっちにきたみたい。」
「わ〜なんかすごい複雑な話になりそうだね。
ねぇ、おばあちゃん、今日あったキム・ソルジュさんが、おばあちゃんに会いたいって言ってるんだけど」
美園は愛子の顔色を伺いながら本題に入った。
それは愛子のふっと見せる切なげな表情に触れてはいけない何かがあるような気がしたからだ。
いやもしかしたらそれは美園の想像が感じさせていたのかもしれない。
「その方に会いましょう。」
愛子は何かを吹っ切るように元気な声で言うと美園の顔を見てニッコリと笑った。
「これ、彼にもらった名刺なんだけど、おばあちゃんにわたしとくね」
そういいながら名刺を差し出すと
「いいわ、これはあんたがもっていてちょうだい。連絡しなきゃいけないでしょう。
私はね、ただその方にあってキンさんにお世話になったことのお礼をいいたいだけだから」
愛子はそういうと
「もう寝るわ。私はいつ来ていただいてもいいから向こう様のご都合を聞いて教えてちょうだい」
と、のみ残しのオレンジジュースを持って自分の部屋に入っていった。
「おやすみなさ〜〜い」
美園はそういうと一人、大きなため息をつきながらそのまま畳の上に大の字になってねころんだ。
翌日、会社に出勤した美園は昼食時間にキム青年の名刺を取り出し携帯に連絡を入れた。
「ヨブセヨ」
ドキドキしながら相手が出るのを待っていた美園はいきなり聞きなれない言葉が飛び出したので
思わず携帯をきってしまった。
「うわ〜どうしよう。」
慌てふためいて、ウロウロしながら携帯を握り締めていると着信音が鳴り出し
その音に驚いて床に落としてしまうと言う、どうにも落ち着きのない行動を取ってしまっていた。
「もしもし?」
美園はキャッチボタンを押すとおそるおそる声をだしてみた。
「もしもし、私は、キム・ソルジュです。この番号は美園さんですか?」
低音だが滑らかなその声に、
「あ、はい美園です。お時間よろしかったでしょうか?」
あわててそう答えると
「はい、よろしいですよ。」
携帯越しの相手の笑顔が見えそうな優しい声で冗談ぽく返って来た。
その対応に美園は胸をなでおろし深呼吸をして
「昨夜。あなたのことをおばあちゃん、いや、あの祖母に話しました。
それで、そちらのご都合の良い日に何時でもいらしてください。っていってます。」
と用件を伝えると
「おお〜それでさっそく返事をくれたんですね。ありがとう。
わかりました。今、僕は東京にいます。
仕事のスケジュールを見てまた美園さんに連絡しますからよろしくおねがいします。」
よほど嬉しかったらしく声のテンションがあがっている。
「それでは、おまちしています。さよなら」
美園はそういうと携帯を切った。
キム・ソルジュの天真爛漫な明るさをその姿に重ね合わせて美園の鼓動が脈うちはじめ
これ以上話しているとおかしくなってしまいそうで勤めて冷静をよそおってしまっていたのだ。
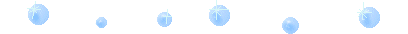
出会いとは不思議なものである。ある日突然、その場所に居合わせても通り過ぎる縁もあれば、
呼び寄せられるように繋がっていく縁もある。日本人岡野美園と韓国人キム・ソルジュの出会いは
まさに奇異な運命の糸に手繰り寄せられるように繋がっていくことになる。

